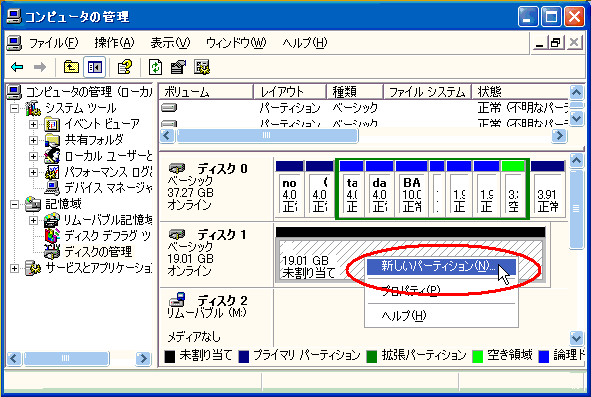
パーティションの作成(ディスクの管理の使い方)
[新しい基本領域、拡張領域の作成]
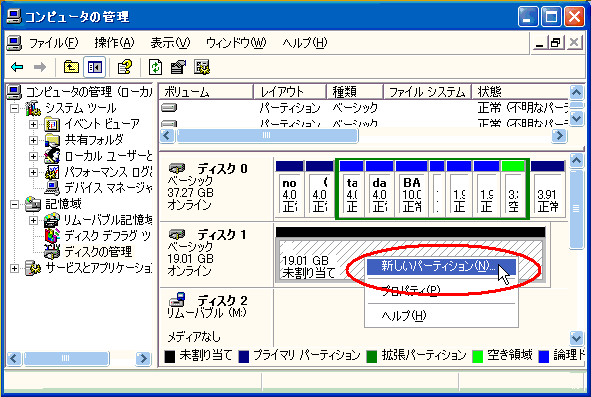
論理領域(論理ドライブ)を作成する場合は、拡張領域を作成した後で拡張領域中の「空き領域」の右クリックメニューから「新しい論理ドライブ(N)...」を選択する。
[新しい論理ドライブの作成]
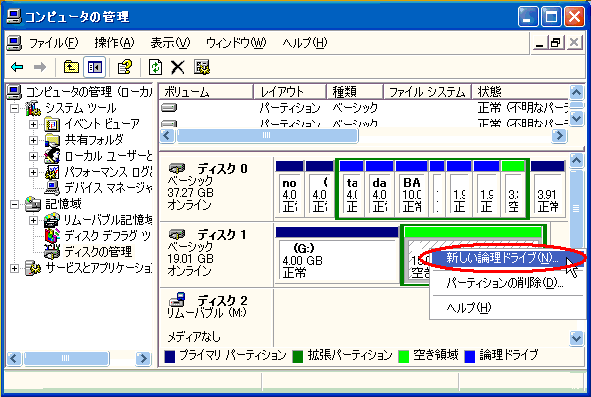
いずれの場合も下記のように「新しいパーティションウィザード」が開始される。作成する領域の種類によって若干違うが、多くは共通なのでまとめて説明する。種類によって違う場合は都度その旨解説する。
[新しいパーティションウィザード開始画面]
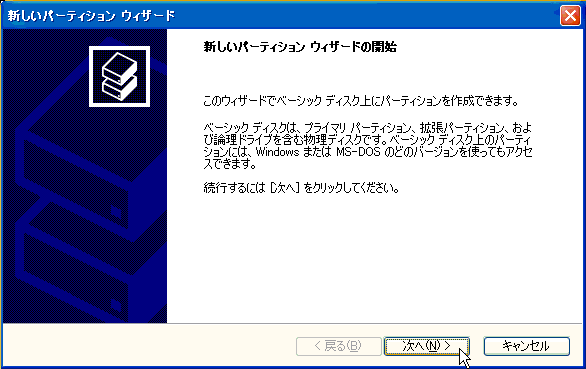
ここでは「次へ」をクリックする。
まずパーティションの種類の選択を行う。基本領域(プライマリパーティション)、拡張パーティション、または論理領域(論理パーティション)かの選択を行う。
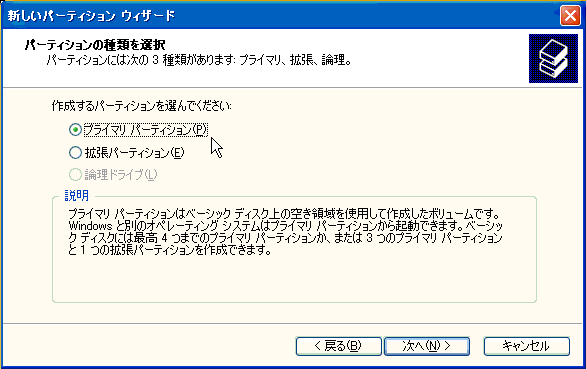
「未割り当て」領域を選択して新しいパーティションウィザードを開始した場合は、当然だが基本領域(プライマリパーティション)と拡張パーティションしか選択できないようになっている。逆に拡張領域内の「空き領域」を選択して開始した場合は、論理ドライブしか選択できないようになっている。パーティションの種類を選択したら「次へ」をクリックする。
次はパーティションのサイズの指定になる。
[パーティションサイズの指定]
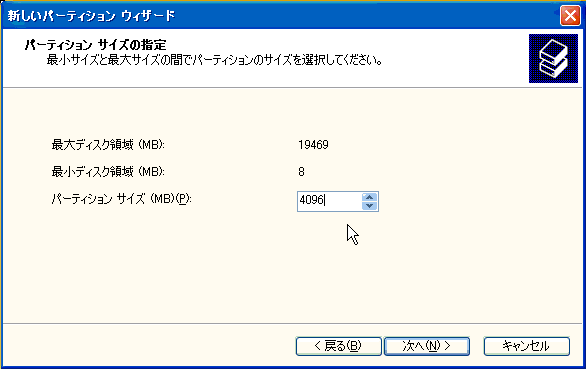
割り当て可能な、最大サイズと最小サイズが表示されているので、その範囲内でサイズを指定する。デフォルトで最大サイズが入力されているが、必要に応じて変更してほしい。サイズが決まったら「次へ」をクリック。
次に作成パーティションが拡張パーティション以外の場合(つまり基本領域か論理ドライブの場合)、ドライブレター(ドライブ文字)を割り当てを行う。
[ドライブ文字またはパスの割り当て]
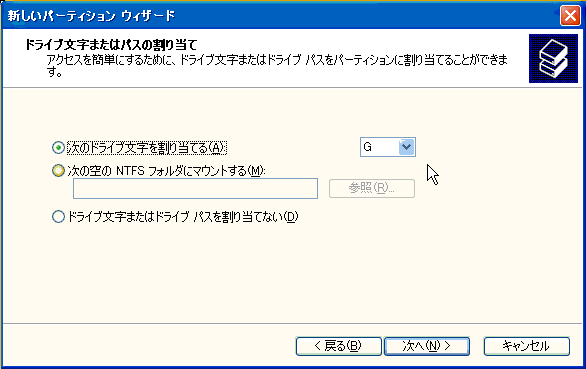
ここではドライブレターを割り当てないこともできるが、普通は割り当てるだろう。またNTFSフォルダに割り当てることもできるがここでは説明しない。
適当なドライブレター(デフォルトでは最も若いものが選択されている)を選んで「次へ」をクリック。
次もやはり拡張領域以外の場合、このパーティションをフォーマットすることができる。
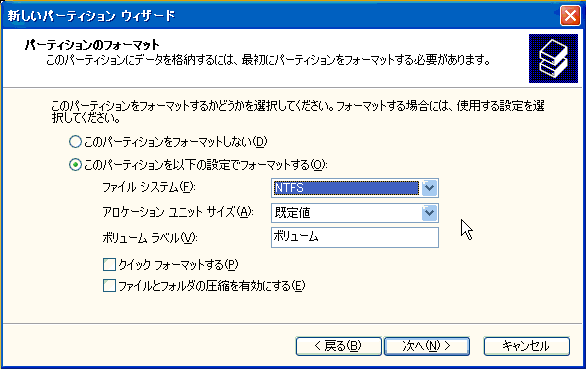
「ファイルシステム」にはFAT(16)、FAT32、NTFSが選択できる。「アロケーションユニットサイズ」は、いわゆるクラスターサイズなのだが、これの意味が分からない人は「既定値」にしておこう。「ボリュームラベル」はデフォルト(ボリューム)のままでも好きなものに変えてもいいだろう。
「クイックフォーマット」を選択するとフォーマットが非常に速いのだが、初めてパーティションを作るときは選択しないでほしい。圧縮に関しては必要ならばチェックしてもいいだろう。これも意味が分からない人はチェックしないでほしい。
ここではフォーマットをパスすることもできるが、いずれ必要なことなのでやってしまった方がいいと思う。すべて選択したら「次へ」をクリック。
最後に指定を行ったことの確認画面が出る。最初のうちは一応確認しておこう。

完了をクリックすると、基本的にパーティションの作成は完了だ。フォーマットするように指定していた場合、即座に作成パーティションのフォーマットが開始される。
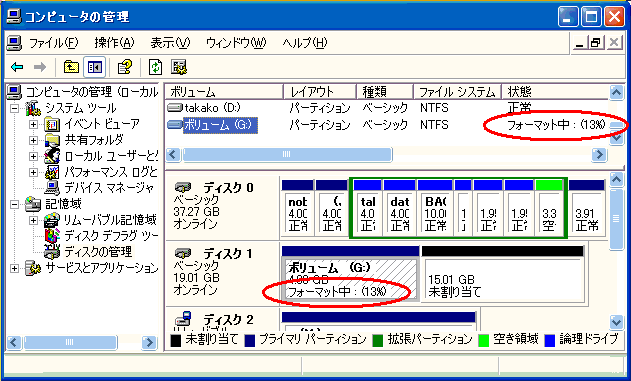
フォーマットが完了するまで、なるべくおとなしく待っていよう。